戦後80年
〜都留の戦争体験者が語る”記憶”と”提言”〜


戦後80年
今年(2025年)は戦後80年。ミュージアム都留で「都留・平和のための戦後80年展」と題した企画展が開催中(8月31日まで)。市内の戦争に関する記録や資料、戦争体験者や親族による”記憶”をまとめた展示などがあり、改めて平和について考えるきっかけにしてほしいとのこと。
実は、つるのルーツスタッフの親族にも戦争体験者が。都留市田野倉で生まれ育った中村さん(97)です。戦地には行かず、田野倉や関東甲信で過ごしていたという中村さん。記憶をたどって、お話を聞かせてくださいました。
◆中村邦彦(なかむらくにひこ)さん◆
1927(昭和2)年9月24日生まれ。現在97歳。田野倉の農家で生まれ育ち、戦時中は逓信省(ていしんしょう・のちの日本電信電話公社・現NTT)で通信士の勉強、就職、講師をも務める。戦後は精米所やガソリンスタンドの経営などをしながら、戦争孤児支援などを行ってきた。
戦争の記憶
戦時中、実家の田野倉や逓信省の施設(現・東京都調布市、長野県茅野市、山梨県大月市)で過ごされていたという中村さん。まずは、記憶にある戦争の景色をお聞きしました。
のり:今も覚えていることを教えてください。
戦争の頃、歳は18か19だった。東京の郊外(現・調布市)の寮で勉強していたときは、空襲があって。自分たちはちょっと郊外で安全なところだったからな。空襲を受けているのにおっかなくない。実際に体験しているのに、していないような、どこか不思議な感覚。でも、空が明るくなって「あぁ、燃えている」って分かった。
人間には、おっかないものを見たい気持ちもあって、防空壕にいると、若者は様子が見たくて外へ出てくる。外から来た人は中に入りたい。だから入口で、片方は「おっかねえぞ!」って言って、もう片方は「やいやい!見せろ!」ってね。そんな時代だった。でも、そのうち東京の郊外も危ないということで、長野の茅野にある寮へ疎開が決まった。
のり:都留にいたときに、戦争を感じたことはありますか?
実家(田野倉)にいたとき、ちょうど甲府の空襲があって。空が明るくなって、甲府のほうが焼けているんだって分かったね。
都留は空襲を受けていなかったけど、大月が爆撃された。爆弾が落ちて、何人か亡くなったって聞いたし、鉄砲で撃たれた人もいたな。その頃はみんな、大月は田舎だから安心だと思っていたよ。こんなところにアメリカの飛行機が来るなんて思っていないから。
大月に爆弾が落ちても、音なんて気が付かなかった。戦争中は、あっちもこっちもドカン!ドカン!ってやっていたから音に慣れちまって、いちいち反応しなくなってたんだな。
のり:中村さんは、東京から長野へ疎開されたとのことでしたが、都留に疎開してきた人はいましたか?
東京から都留に疎開してきた人は大勢いた。東京に住んでいる親戚の半分くらいは子どもをこっち(都留)に預けてきたかな。うちでも何年か預かっていた。親は東京で仕事をしないといけないけど、子どもは少しでも安全なところに、というふうに、親戚を頼って疎開してくる人が多かった。うちだけじゃなくて、周りにもそういう家はたくさんあったよ。
戦地に行かない人の暮らし
のり:中村さんご自身やご家族、ご友人などは戦地に行かれたのですか?
戦地には行ってないな。でも、俺よりも年上の人はほとんどが戦争に行っているか、行かなかった人は徴用で軍需工場に連れていかれた。都留には女性と子どもばかりしか残らなかった。親父にも呼び出し状みたいなものが来て、軍需工場へ働きに行くことになったよ。
俺の仲間は、歳が18~19歳で、ちょうど兵隊に行くちょっと前の歳だったから、「満州義勇軍」に志願して行った人が多かった。義勇軍って表向きは農民としての開拓団だけど、実際はいつでも兵隊になれるような組織でね。農業をしながら戦争の準備をしてるようなもんだった。
俺はたまたま親父が「国の方針で戦争に連れていかれると困る、長男だからうちの近くに置いておきたい」ということで、のちの電電公社(現在のNTT)に入ることになったんだ。公共の仕事に就けば、徴兵されにくいって言われていたからね。
うちは8人兄弟で、弟たちは東京の名門大学で勉強したり、妹たちは就職したり嫁いだりしていて、親父の兄弟(叔父たち)が東京で商売をしていたから、その子どもたちが疎開してきたね。
のり:中村さんはどんな暮らしをされていたのですか?
電電公社には、将来通信生になるだろうという気持ちで寮に入って勉強したね。俺は、小学校卒で使い物にならないから、中学校卒のようにレベルを上げるんだと言われて、英語や物理を教わって、「モールス信号」っていう、短い音と長い音を組み合わせて文字を伝える通信方法も覚えた。例えば「トン・ツー、トン・ツー」って具合にね。便所に行っても、壁を叩きながら覚えるわけだ。そうすると、壁越しに仲間とモールス信号で会話ができて、それがまたおかしくてな。今思えば笑えるけど、当時は楽しいと思う余裕はなかったよ。それでも、そんなふうに勉強させてもらえたっていうのは、ある程度は特別に配慮されていたってことだと思う。
何で東京や長野にいたかというと、当時は、電話の仕組みが今とは全然違っていて、声を遠くまで届けるには「増幅器」っていう装置で音を大きくしながら送らなきゃならなかった。だから、およそ50キロごとに「中継所」っていう設備があって、東京の郊外にひとつ、大月にひとつ、さらにその先の茅野にもあって…というふうに、長距離の通話にはいくつも中継所を挟む。その中継所で勉強しながら働いていたわけだ。中継所にはラジオのような機械があって、電話の音を増幅するだけじゃなくて、会話の内容もその場で聞けるんだ。だから、仲間の中には、それを利用してこっそり人の通話を聞いて楽しんでるやつもいたよ。今なら問題になるだろうけど、当時はそんな時代だった。
それに、機械を動かすのに大量の電池が必要で、それがアルカリ性だから、作業をしている時に服にその液が付くと、すぐ服がボロボロに傷んじゃって、そういう過酷さもあったね。
とはいえ、勉強だけじゃなかった。たまには軍隊の訓練みたいなこともさせられた。訓練用の鉄砲を持って、「担げ!」「頭が高いぞ!」なんて怒鳴られながら地面を這って進む訓練もしたし、お寺に連れて行かれて、座禅を組まされたこともある。そうやって、身体も精神も鍛えられていた時代だったんだね。
のり:戦地とは違う苦労がたくさんあったのですね。
戦地へ行った人も行かない人もみんな戦争一色で、「お国のために」という気持ちで一生懸命だったよ。

※当時都留市内での出征時の様子(画像提供「ミュージアム都留」)
長野の茅野にある寮に入っていた頃は、1か月くらい家に帰れなかった。そうするとうちが恋しくて帰りたいわけだ。だから、たまに帰れるとなると、もう嬉しくてね。茅野から大月まで電車に乗って、列車の中でだんだん先頭の車両のほうに移動していくんだよ。座ってた場所から少しずつ前へ前へと移っていって、最後には一番前の車両にいたりする。おかしな話でしょ。列車なんて、どこに乗っても到着時刻は同じなのに。大月に着いたら、なんだ、出口から一番遠いじゃないか!って。今思えば、帰りたい気持ちが体に出ちゃってたんだろうな。
のり:本当に、家族が恋しくてたまらなかったのですね。そういう方は、きっと戦時中には大勢いらっしゃったのでしょうね。他につらかったことはありますか?
つらいことはいっぱいある。一番は、物がない。腹は減ってるのに食うものがない。
休みの日には、腹が減っているから、何か腹に入るものを見つけようと買い出しに行くけど、農家だって物がないから売ってくれない。一度だけ、ある家が山芋を売ってくれたんだけど、寮に戻るまでに食べきってしまって、今度は腹がいっぱいで寮のごはんが食べられない。だから部屋に持ってって、仲間に見つからないよう隠れて食べたよ。
他にも、雪が降る日に山に行って自生している木の実を取って食べたり、実家に帰ったときには母親に「何か食うものをくれ」ってねだったりしたな。でもその頃は、俺ばっかりじゃなくて、どこだって食料が無いから、みんな腹をすかせていた。
戦後の記憶
のり:終戦後のこともお聞きしても良いですか?
疎開してきた人たちが東京へ帰るんだけど、持ってきた荷物はリュック一つだけだったから、それをまた背負って帰るんだ。俺は、その人たちを車で東京まで送ったよ。
のり:車をお持ちだったのですか?
東京の焼け野原に一台残っている車があったから、ボロボロだったけどそれを買ってね。ここらに車なんてなかったから。免許もないし、人に教わったまま乗った。駐在所で「車買ったけどどうしたらいい?」とおまわりさんに相談したら、免許証のようなものをくれて。昔は、おまわりさんと一般の人が仲良しで、本当によく助けてくれたよ。
のり:都留の町はどんな様子でしたか?
この辺は昔、全く何もなくて、夜なんか真っ暗で通るのが怖いくらいだったよ。原っぱでな、俺はそこにポツンと、タンクだけのガソリンスタンドを作ったんだ。車もない時代だから、たまにしかお客さんは来なかったな。
その頃、同級生が近くにドライブインを作るって言いだしてさ。
俺はその土地交渉をして、自分は精米所もやってたけど、それだけじゃ食えないし、ガソリンスタンドも始めたんだ。
でも、ここらは道も舗装されていなくてガタガタで、東京へ行くと道も綺麗で「いいなぁ」と思ったもんだよ。
のり:終戦後、特に印象に残っていることはどんなことですか?
戦争中は、勝たなきゃだめだ、贅沢は敵だと言って、みんな戦争一色になるわけだ。それが終戦になると、戦争一色がぱっとなくなって、個々がバラバラになってしまうし、混乱期もあった。考えが全部戦争に向いていたのが、負けてからはみんな考えがぼやけてしまい、自分はこれからどう生きようかと。生きる目的が変わってくるよな。
だから、戦後はぼやっとした時間があって、ソ連(旧ソビエト)から引き揚げてきた人たちが村の青年を捕まえては、共産主義の良さを説いて回っていたよ。でも俺は、それぞれが持っているものを、貸したり借りたり、みんなで共有して使おう、助け合って生きていこうよという考え方だったから、そういう青年たちとはよく議論をしたな。俺は「人のために」というのを大事にしたくて、色んなことをやってきたよ。戦争孤児の支援もしたし、遠山正瑛先生(日本沙漠緑化実践協会など)の「緑の協力隊」の活動にも参加して、モンゴルの砂漠に植樹を行う活動にも参加した。もちろん地元のことも、谷になっていたところを埋め立てて道路を通すとか、トンネルをつくるとか、そういうのを進めるのに協力したよ。誰かの役に立てるってのは、やっぱり嬉しいな。支援した中国の子はもう立派な大人になったけど、今でも俺のことをお父さんって慕ってくれて、時々会いに来てくれるのも嬉しいよ。
戦争体験者として今思うこと 立ち止まって考えることや心を豊かにすることの大切さ
 のり:今年、戦後80年ということで、戦争体験者として何か思うことはありますか?
のり:今年、戦後80年ということで、戦争体験者として何か思うことはありますか?
戦争は、人間の心を蝕む。自分たちの心も相手の心も。だから戦争はやっちゃいけない。でも、争いはなくならない。どうしたらなくなるか?というと、大変難しい。戦争がなくなるためには、「他を許す」ということが大事かな。「私とあなたは違うけど、社会は違う人間同士で構成しているもので、共通点をみんなで見出していきましょう」という勉強がこれからは必要かもしれない。心を養うってことが。
そのためには、「自分とは、人生とは何ぞや」という大事な根っこを持つことだな。今は、物が溢れて、せわしない時代だから、立ち止まって考えるのが難しくて、流されてしまう。
戦争中は、戦争は良いことだという風潮に流されていたし、戦後すぐの混乱期もじっくり考える余裕がなかった。よっぽどでないと、立ち止まって、自分は流されないぞと言える人間はいなかった。
でも俺は、だんだん考えられるようになった。そのきっかけは、文学にふれたからだと思う。本を読んだり、俳句を詠むことで、自分の心と向き合うようになった。何を見ても何も感じないというようじゃ、良い作品は作れないからね。立ち止まって考えることで心が豊かになるから、そんな時間がとれる世の中になってほしいよ。
<取材後記>
 中村さんのお話をお聞きして、改めて考えさせられたことがあります。
中村さんのお話をお聞きして、改めて考えさせられたことがあります。
豊かさって何だろう?
親が子どもにしてあげられることって何だろう?
自分の人生って何だろう?
この「何だろう?」こそが、戦争体験者の中村さんが今必要だと思うことであり、答えを考え続けることが、戦争という悲しみを減らす方法なのかもしれません。取材中には、辛い経験を思い出し、時折涙ぐむこともありながら、本当にたくさんのお話を聞かせてくださりありがとうございました。
戦争体験者やその家族の記憶が展示されている企画展「都留・平和のための戦後80年展」は、8月31日(日)まで、ミュージアム都留で開催されています。入館は無料です。ぜひ出掛けてみてください。



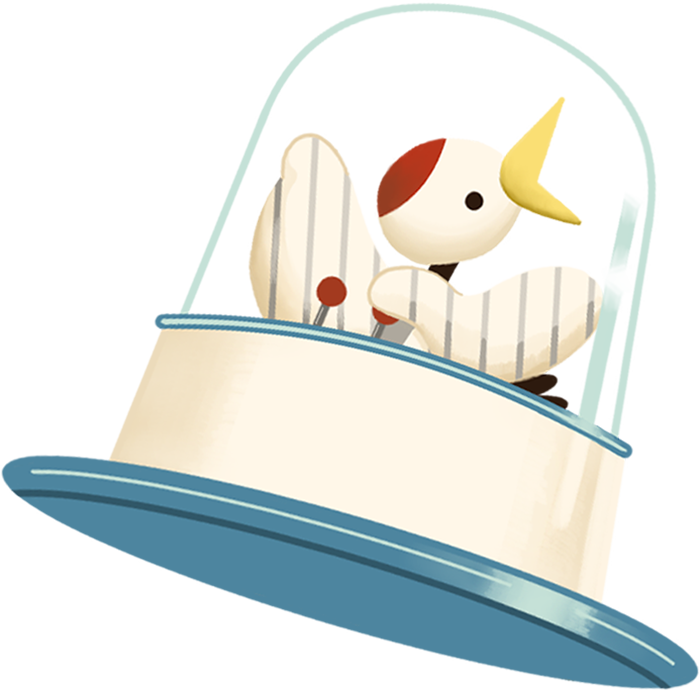




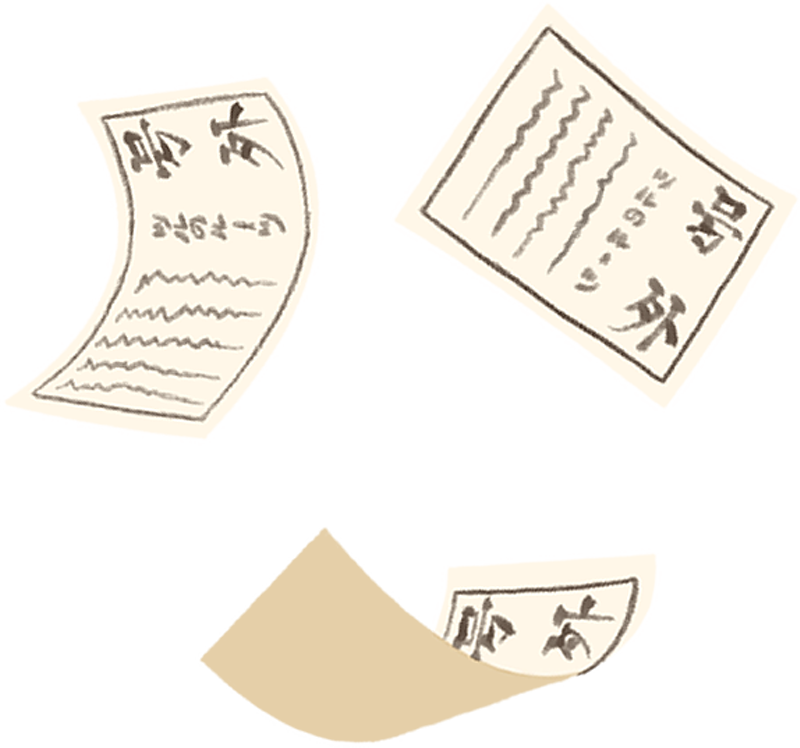
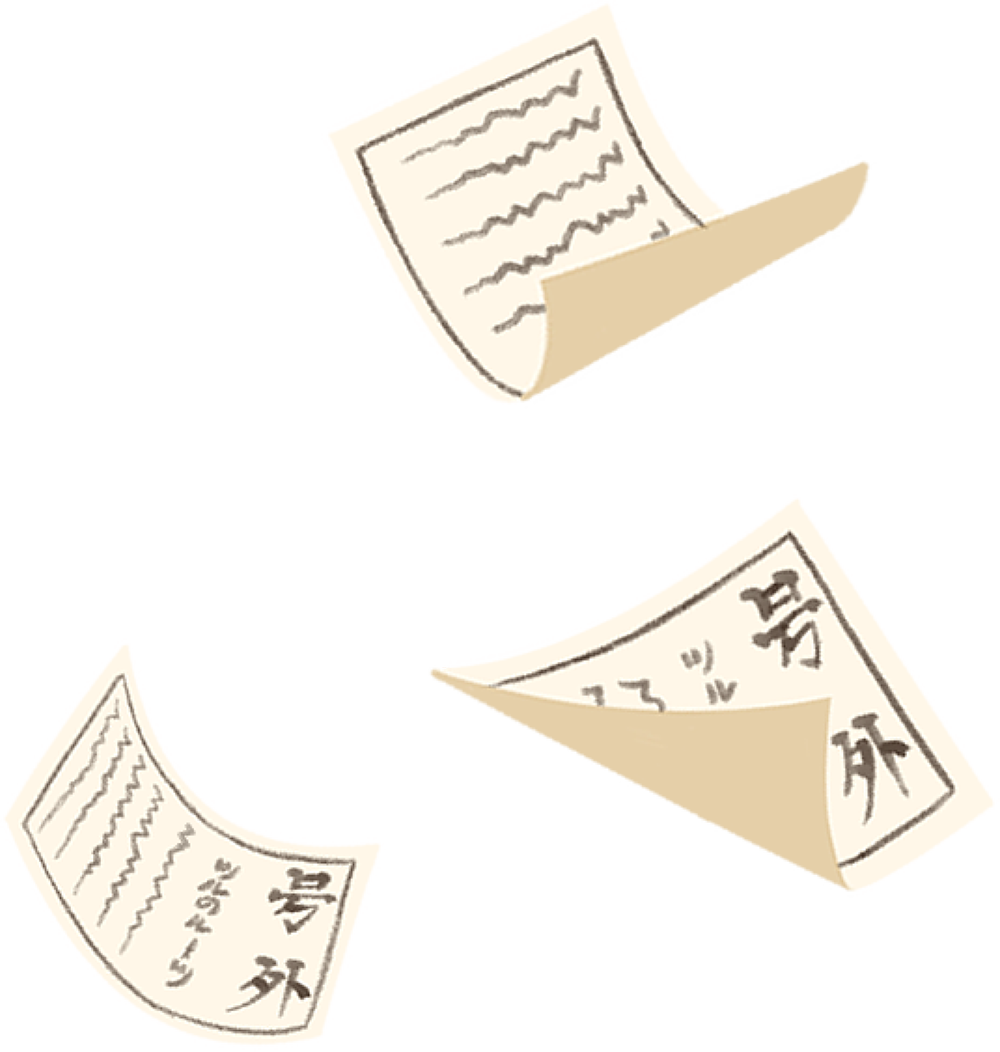
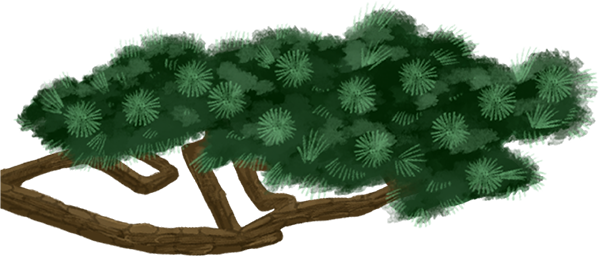
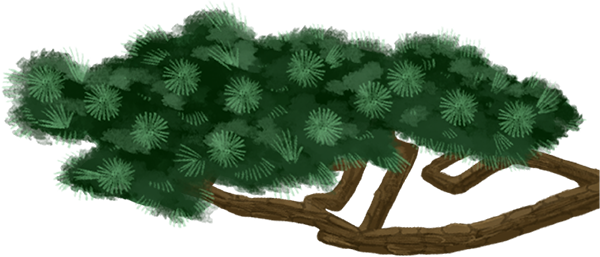











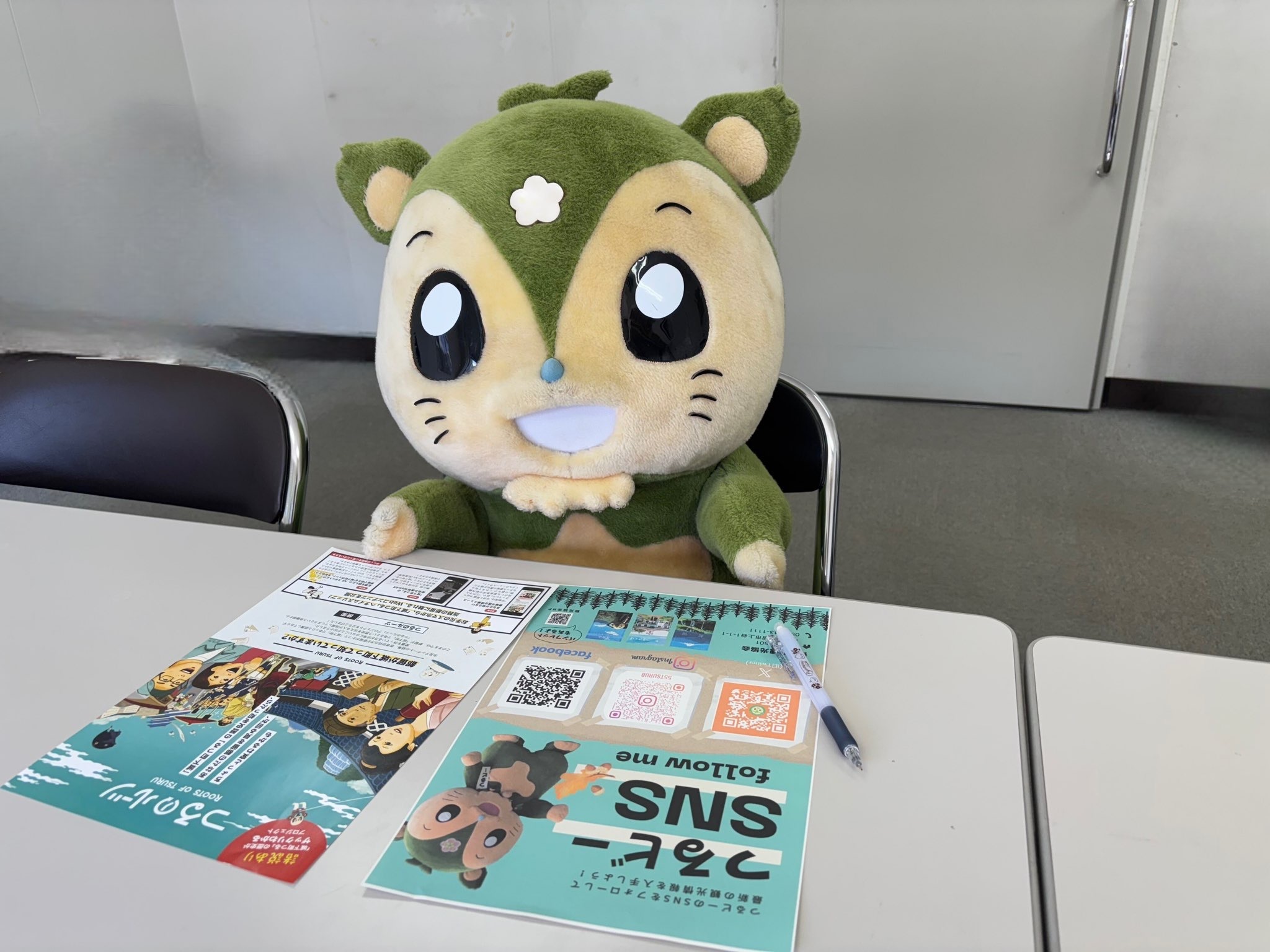


コメント
負けてからはみんな考えがぼやけてしまい、生きる目的が変わってくるという言葉は、失われた30年以降の現代日本にも通じるものがあると感じました。
働いても報われづらい社会の中で、行き場のない不満が排外主義的な政治思想に流れてゆくのも、ある種の必然なのでしょう。信じられるものがわからないから、誰かのせいにしたくなってしまう。
極端な情報が飛び交い、アルゴリズムで分断が深まる恐ろしい時代になりました。だからこそ、一方の見解に偏らず、自分の頭でバランスよく考え続ける姿勢が、平和を維持するためにとても大切なのだろうと記事を拝読しながら感じました。
貴重なインタビュー記事を、ありがとうございました。
私のお父さんも兵隊で今でも家に出征するときの写真が残っています。満州に行って足を打たれて穴が空いていました。私達子供ころは軍歌聞いて育ちました❗都留がこんどだというときに終戦になりました。思えば大変な時代でした。あれから80年世界で今でも戦争が有ります。早く終わって欲しです。それを願っています❗